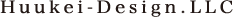ローコスト住宅のメリット、デメリット。
実例と間取りや注意点、向いている人を解説


「家を建てたいけれど、予算が限られている」
「住宅ローンの負担を軽くしたい」
そんな悩みを抱えている方におすすめなのがローコスト住宅。
1,000万円台でも家を建てられるローコスト住宅は魅力的な選択肢となりますが、安さから品質や住み心地に不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、ローコスト住宅のメリット・デメリットから向いている人の特徴、後悔しないための注意点まで、風景のある家で手がけたローコスト住宅の実例も含めてお伝えします。
ローコスト住宅とは
ローコスト住宅とは、一般的な注文住宅に比べて建築費用を大幅に抑えた住宅のことです。「低価格住宅」とも呼ばれ、必要最低限の機能や品質を確保しつつ、設備や仕様の選定、間取りの工夫、施工の効率化などによって無駄を省き、コストダウンを図っています。
1,000万円台で建てられるケースも多く、初めて家を持つ若年層や子育て世代にとって、経済的な負担を抑えながらマイホームの夢を実現できる選択肢となっています。
最近では、ローコストでありながらもデザイン性や快適性に優れた住宅も増えており、「価格を抑えつつ自分らしい暮らしを叶えたい」というニーズに応える住まいとして注目されています。
ローコスト住宅のメリット
ローコスト住宅のメリットは、住宅ローンの負担を大幅に軽減できることです。一般的な注文住宅と比べて約半額で建築でき、借入額が削減されるので月々の返済負担が軽くなります。
契約から引き渡しまでの期間も短いため、引っ越し時期が決まっている場合でも計画的な住み替えが可能です。また、ローコスト住宅は基本構造を簡素化した設計となっているため、こだわりたい部分に予算を集中できるほか、打ち合わせ回数が少なくてすむ点もメリットとしてあげられます。
ローコスト住宅のデメリット
ローコスト住宅のデメリットとしては、間取りやデザインの自由度が低い点があげられます。コストを抑えるために標準仕様のグレードが低く設定されており、断熱性能や耐震性能などの住宅性能に不安を感じる方もいるでしょう。
設計が規格化されていることから、オプション追加費用が割高になりがちで、予算を超えてしまうケースもあります。また、設備のグレードを抑えているため、一般的な住宅と比べて頻繁にメンテナンスが必要になる可能性がある点もデメリットとしてあげられます。
ローコスト住宅の実例5選
ここでは、風景のある家が実際に手がけたローコスト住宅をご紹介します。
多数の海外メディアでも紹介されたローコスト・ハイクオリティ住宅

- 極限までコストダウンしてほしい
- 外周に窓をなるべく取りたくない
- 革工房を併用したい
- コストダウンのため既製品を一切使用せず、使用する素材は安易に手に入る材料とした。外壁には波板、内装にはベニヤ、木毛板、コンクリートといった工業製品を仕上げなしで採用しハイクオリティな空間とした
- 外周には窓を取らずにインナーコートから光を取り入れる設計手法を採用した。インナーコートの床面に水を張り揺らぐ水面が自然光をほどよく反射させて室内の隅々まで光が届く設計とし
- インナーコートを介して住居部分と工房に分け、ガラス越しに各々の気配を感じ取れながら別空間を尊重できる空間とした
- 風景のある家がローコスト・ハイクオリティ住宅を設計するきっかけとなった住宅で、予算1000万円でロフトやバスコート、置きバスと贅沢な建築とした
仕上げをそぎ落としコストを抑えたハイクオリティ住宅

- 風景のある家が手掛けた「革工房の音色」のようにコストを抑えた家が希望だが特徴を出した
- 敷地が限られているので広く感じる空間にしてほしい
- 隣地に家が建っており窓を開けても光が入らないが、自然光が入るようにしてほしい
- 工事をする業種を極限に減らしできる限り大工工事で完結できるように設計した。デザインはネイビーカラーの尖り屋根を採用して建物の外形を模った玄関ポーチとした
- 一見閉鎖的に感じる外観とは反対に、エントランスを入るとすぐに一坪の光庭、キッチン奥には1.5坪のバスコートを兼ねた光庭を設けて広がり感と自然光が入るように設計した
- 尖り天井の小屋組みの構造をすり抜けるように自然光が注ぎ込んで森林の中の木漏れ日のような雰囲気を醸し出すように設計した
ミニマム店舗設計による増築

- 店舗としてコストを抑えたい
- 店舗としてできる限り多くの商品を展示したい
- コストダウンのため既製品を一切使用せず、使用する素材は安易に手に入る材料とした。外壁には波板、内装にはベニヤ、木毛板、コンクリートといった工業製品を仕上げなしで採用しハイクオリティな空間とした。
- コストの範囲内で天井をできる限り高くし壁面にも商品を展示できるようにした。また展示什器はコストを抑えるため大工工事で作れる什器家具とした
中庭を眺めながら回遊できるローコスト住宅

- 子供たちが走り回れる家にしたい
- 完成させず未完の家にして少しずつDIYをしていく楽しい家にしたい
- 中庭を大きく設けて玄関・LDK・廊下を中庭を中心に走り抜けられるような設計にした
- コストを抑えながらDIYの可能性を残すために壁はベニヤ、床はコンクリート(基礎のまま)、天井は構造材むき出しとして最小限の仕上がりとした
自然を感じられる暖炉と土間のあるローコスト住宅

- コストを抑えた家づくりをしたい
- 自然を感じられる家にしたい
- 余白を感じられるようにしたい
- コストを抑えるため内外仕上げに焼き板とスレート、コンクリートブロックなどを採用した
- 庭の畑に面して全面ガラス戸とし全開口で開放できるように設計した
- 屋根と壁の接点にもガラスをはめ込み、空を見ながら生活できるよう工夫した
- 二つの四角をずらすように平面計画をし、あえて平面上余白が生まれるように設計した。生まれた余白は裏庭として風と光が入るようにし、また片流れ屋根を利用して小屋裏的ロフトが生じるようにした
ローコストで住宅を建てるならどんな構造・間取りがよいか
ここでは、ローコスト住宅におすすめの構造・間取りをご紹介します。
平屋
平屋は、基礎面積と屋根面積が同じになるため構造がシンプルで、建築費用を抑えやすいという利点があります。階段が不要なため居住面積を有効活用でき、バリアフリー設計で将来的にも安心です。ローコスト住宅にする際は、水回りを中央に集約したコンパクトな間取りや、廊下を最小限に抑えて居住スペースを広げる間取りがおすすめです。また、正方形に近い形状にして外壁面積を減らすと、建材費と施工費の削減にもつながります。
総二階建て
総二階建ての場合は、建物の形状を正方形や長方形にすると、外壁面積を最小限に抑えられ、建材費と施工費を削減できます。シンプルな形状であれば、施工期間も短縮でき、人件費を減らせるでしょう。また、屋根形状もシンプルになるため、雨漏りリスクも低減できます。総二階建てであれば、限られた敷地で床面積を確保できるので、都市部の狭小地でも建てやすいです。
箱型(キューブ型)の家
箱型(キューブ型)の家は、無駄のないシンプルなデザインが人気のため、建材費を抑えられます。また、四角い形で柱やつなぎ目が少ないことから、ローコスト住宅でも耐震性をしっかり確保したい人におすすめの選択肢となります。敷地が狭い場合でも、屋上を設置すれば洗濯干しやガーデニングスペースとして活用できるので、建築費を抑えながらゆとりのある居住空間を実現可能です。
間取りを最小限にした家(オープン間取り)
オープン間取りは、壁や仕切りを最小限に抑えた開放的な設計のことです。間仕切りや壁を少なくすることで、建材費・施工費を削減したり、電気配線工事なども簡素化できたりするため、ローコスト住宅に適しています。床面積が限られていても、広々とした空間を演出しやすく、実際の床面積以上の開放感を得られるでしょう。個室が必要な場合は、カーテンなどを活用すれば、プライバシーを確保しながらもコストを抑えた家づくりができます。
規格住宅
規格住宅は、あらかじめ用意されたプランから選択する住宅で、ローコスト住宅に多いプランとなります。規格住宅で、よりローコストな家づくりを実現したい場合は、標準プランをベースにしてオプション追加をなるべく控えると良いです。そのほかにも、間取り変更をやめてシンプルな仕様にしたり、打ち合わせ時間を削減したりすると、工期短縮とコスト削減につながります。
片流れ屋根の家
片流れ屋根は一方向に傾斜した屋根形状で、構造が単純で使用する建材も少なくすむため、ローコスト住宅を実現しやすいです。雨どいの設置も一方向のみで良く、メンテナンス性にも優れており、長期的な維持費用の削減も実現できます。
また、屋根裏空間をロフトや収納スペースとして有効活用すれば、無駄なスペースが無い収納力に優れたローコスト住宅になります。
ローコスト住宅が向いている人
ここでは、ローコスト住宅が向いている人の特徴をお伝えします。
コストを最重視して家を建てたい人(価格を抑えたい人)
住宅購入でコストを最優先に考える方には、ローコスト住宅が適しています。ローコスト住宅は、一般的な注文住宅の半額程度ですむため、経済的な余裕が生まれます。 価格を抑えて住宅を購入することで、病気などの不測の事態にも対応しやすくなり、日々の生活にも安心感がもたらされます。浮いた資金を子どもの教育費や老後資金に充てることもできるので、家族全体の生活設計がより安定するでしょう。
住宅購入が初めての人
住宅購入が初めての人は、ローコスト住宅から始めることをおすすめします。住宅購入は人生の中でも大きな買い物となりますが、ローコスト住宅であれば借入額も抑えられるため、経済的なプレッシャーを感じにくくなります。住宅に対する具体的な希望が定まっていない場合でも、実際に住んでみることで生活上の優先順位が明確になり、次回の住宅選びにおける判断基準として活かせるでしょう。また、ローコスト住宅購入を通して、不動産取引の基本知識を得られるので、将来的な住み替えの際にも安心です。
住宅に過度なこだわりがない人
住宅のデザインや間取り、設備に特別なこだわりがない方は、ローコスト住宅が向いています。ローコスト住宅は、標準的な仕様やプランが予め決まっているため、必要最低限の機能が揃った家を手軽に手に入れられます。また、シンプルな構造でメンテナンスが比較的簡単なので、長期的な維持費用を抑えられる点も、住宅に対するこだわりが少ない人にとって大きなメリットとなるでしょう。
将来的に家を建て替える人、長く住み続ける予定がない人(短期・中期的な住まいとする人)
将来的に家の建て替えを検討している人や、転勤などで長く住み続ける予定がない人には、ローコスト住宅が向いています。ローコスト住宅は、住宅ローンの返済負担が軽くなるので、月々の支払いに余裕を持ちながら、将来の住み替え資金を積み立てることができます。5年から15年程度の中期利用を前提とした住まいであれば、売却時の資産価値の下落も比較的緩やかで、次の住宅購入時の資金計画にも大きな影響を与えにくいでしょう。
住宅ローンの返済負担を軽減したい人
住宅ローンの返済負担を最小限に抑えたい方には、支払い総額を抑えられるローコスト住宅がおすすめです。借入額が少なくなることで、月々の返済額も軽減され、生活にゆとりを持てるようになります。また、返済期間を短縮できる可能性もあり、その分、総利息額も減らせるでしょう。また、返済負担が軽いことで、子どもの教育費に資金を充てたり、老後の貯蓄を増やしたりと、将来への備えを確保しやすくなります。
シンプルな間取り、デザイン、コンパクトな住宅を好む人
ローコスト住宅は、コストを抑えるために無駄のないシンプルな設計が採用されているため、シンプルな間取り、デザイン、コンパクトな住宅を好む人に向いています。 ローコスト住宅のシンプルなデザインは、過度な装飾がないからこそ流行に左右されにくく、長期間住んでも飽きがこない住まいを実現できます。さらに、コンパクトなつくりによって日々の掃除も楽になり、快適な生活空間を維持しやすい点も魅力です。
将来的な収入に不安がある人
ローコスト住宅は、収入減少時でも返済を継続しやすいので、将来の収入に不安を抱える人でも安心して購入に踏み切ることができます。例えば、失業や病気などの不測の事態が起きても、月々返済額が少なければ家計への影響を抑えることができます。現状の収入が低い方にとっても、返済負担が軽いことでマイホーム実現への道筋が立てやすくなるでしょう。また、将来的な収入増加が見込める場合は、繰り上げ返済による早期完済も可能なので、ライフステージの変化に応じて柔軟に対応できます。
将来リフォームを考えている人
将来的に大規模なリフォームやリノベーションを予定している方は、ローコスト住宅が向いています。ローコスト住宅を選択し、初期投資を抑えることで、リフォーム資金を確保しやすくなったり、住宅ローンの負担を考慮せずに改修計画を立てられたりします。シンプルな構造のローコスト住宅は、間取りの変更もしやすく、リフォームの自由度も高くなります。段階的に改修を進められるので、ライフスタイルの変化に応じた理想の住まいを実現できるでしょう。
ローコスト住宅で後悔しないための注意点
ローコスト住宅で後悔しないためには、いくつかの注意点を把握しておくことが大切です。以下では、10の注意点をお伝えするので、ローコスト住宅づくりの参考にしてみてください。
総費用(コストを削った箇所、安い理由)の確認
ローコスト住宅選びでは、総費用をしっかり確認することが大切です。表示価格の他にも、電気・給排水・外構工事が別途必要となると、総費用が大幅に増加してしまうケースもあります。また、相談時にローコスト住宅を実現できている理由を確認しておくと良いです。「建材のグレードを下げている」「工程の効率化や大量仕入れによる企業努力」など安い理由を把握することで、将来的なメンテナンス費用を見据えた判断ができるようになります。
アフターサービス・保証制度の確認
ローコスト住宅では、アフターサービスや保証制度の内容を事前に確認しておくと良いです。初期費用を抑えても、保証期間が短く設定されていたり、不具合対応が遅かったりすると、結果的に高額な修繕費用がかかる可能性があります。また、補償対象外の項目が多いケースもあるので、構造保証、防水保証、設備保証の期間と範囲を確認し、定期点検の頻度なども把握しておきましょう。コストパフォーマンスを重視しながら長期間安心して住み続けるためには、充実したアフターサポートが欠かせないので、安心して任せられる業者を選ぶと良いです。
設備・仕様のグレードの確認
ローコスト住宅では、設備や部屋全体の雰囲気を変えられるオプションが用意されているので、何が変更できるのかを事前に確認すると良いです。標準仕様では物足りないと感じる場合、床材のグレードアップや収納の追加をすることで、住み心地を高められます。ただし、オプション追加費用が割高になるケースも多いため、必要なオプションをリストアップし、総費用を計算した上で契約を検討することが大切です。
オプションの確認
ローコスト住宅では、設備や部屋全体の雰囲気を変えられるオプションが用意されているので、何が変更できるのかを事前に確認すると良いです。標準仕様では物足りないと感じる場合、床材のグレードアップや収納の追加をすることで、住み心地を高められます。ただし、オプション追加費用が割高になるケースも多いため、必要なオプションをリストアップし、総費用を計算した上で契約を検討することが大切です。
メンテナンス性・ランニングコストの確認
ローコスト住宅では、初期費用の安さに注目しがちですが、長期的なメンテナンス性とランニングコストも踏まえて検討すると、コストパフォーマンスが本当に良いのか判断できます。例えば、外壁材の塗り替え周期、給湯器などの設備の交換時期を確認してみましょう。安価な建材や設備を使用している場合、メンテナンス頻度が高くなり、結果的に維持費用が高額になる可能性があります。目先の安さだけでなく、長期的な視点での総コストを把握することが、後悔のないローコスト住宅選びにつながります。
耐震、耐熱、気密性
ローコスト住宅であっても、耐震性、耐熱性、気密性のチェックは欠かせません。耐震等級、断熱等級、気密性能(C値)などの数値を参考にし、住宅の性能レベルを見極めましょう。また、断熱性能が不十分だと光熱費がかさんでしまうため、お住まいの地域の気候に合った仕様なのか確認することも大切です。24時間換気システムや結露対策の有無も住み心地に大きく影響するので、これらの設備についても事前に調べておくと良いです。
施工の品質、現場管理のチェック
ローコスト住宅では、コスト削減のために工期短縮を図ることから、施工品質に問題が生じる可能性があります。そのため、施工途中の建築現場には定期的に足を運び、作業の丁寧さや現場の整理整頓状況をチェックすると良いです。また、契約前に現場監督の資格や経験年数、品質管理体制についても確認しておくと、施工時の安心感を得られます。万が一、不適切な施工が発見された場合は、担当者に報告し、施工業者に改善を求めましょう。
業者選び
ローコスト住宅の業者選びでは、価格の安さだけでなく実績と評判をしっかり確認すると良いです。地元での施工実績が豊富で評判の良い業者は、地域特有のニーズに対応でき、アフターサービスも充実しています。また、信頼できる営業担当者を選ぶことも大切です。信頼できる担当者の元、適切なアドバイスや納得のいく説明を受けることで、安心してローコスト住宅づくりを進められるでしょう。
予算と資金計画
ローコスト住宅の購入時は、建物本体価格以外の諸費用も含めた総合的な資金計画を行いましょう。住宅購入には、土地代、外構工事費、登記費用、住宅ローン諸費用、引越し費用、などの費用がかかるので、計算にいれておかないと追加資金が必要となる可能性があります。住宅ローンを検討する際も、借り入れ条件をしっかりと確認し、月々の返済額が家計に与える影響を考慮すると良いです。また、将来の収入見通しを立てたり、子どもの教育費等を踏まえたりしながら、無理のない返済計画を立てましょう。
ローコスト重視にならない
ローコスト住宅選びでは、価格の安さだけを追求して品質や安全性を軽視しないようにしましょう。極端にローコストを追求すると、安価な材料を使用した低品質な住宅になったり、耐震性・断熱性能に問題が生じたりする恐れがあります。ローコスト住宅で起こりがちな問題は、住み始めてから数年経過してから現れるケースも多く、実費負担となる可能性もあります。将来的なトラブルを防ぐためにも、品質面もしっかりと確認した上でローコスト住宅を建てると良いです。
ローコスト住宅の寿命
ローコスト住宅の寿命は、一般的な住宅と変わらず、適切な維持管理をしていれば20年後も住み続けられます。ローコスト住宅は、一般的な住宅に比べて価格が安いことから、「寿命が短いのではないか?」と心配される方もいますが、建築基準法に適合した建物であるため品質に問題はありません。また、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」によると、住宅の構造別耐用年数は、木造の場合22年、鉄筋コンクリート造の場合は47年となっていますが、これは減価償却の基準であり、実際の住宅寿命とは異なります。
実際には、フラット35基準程度で50年〜60年が期待耐用年数と考えられていて、ローコスト住宅であっても、適切な管理を行えば一般的な住宅と同様に長く住み続けられます。
参照:国土交通省土地・建設産業局不動産業課住宅局住宅政策課|期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について
風景のある家がローコスト・ハイクオリティの住宅が実現できる理由
風景のある家では、ローコストを掲げつつも、ハイクオリティの住宅設計が可能です。その理由について説明します。

ローコスト住宅を実現できる理由
①設計段階から暮らし方を重視することで、結果的にローコストにつながる
・小さなお子さまがいるご家庭では、家族の気配を感じやすいよう間仕切りを設けず、大きなワンルームの間取りを採用。これにより工事の手間が減り、コスト削減につながります。
・家族構成やライフスタイルの変化に合わせ、固定壁ではなく可動式の置き家具で空間を仕切る設計を提案。将来的な間取りの変更にも柔軟に対応でき、工事費を抑えられます。
この考え方は特にお子さんがまだ小さいご家族と子育て世代が終了したご家族に当てはまります。一般的に子供部屋が必要になるのは中学生になってからですので、例えば家を建てる時にお子さんが2歳児だった場合10年間は子供部屋は必要なくなってきます。
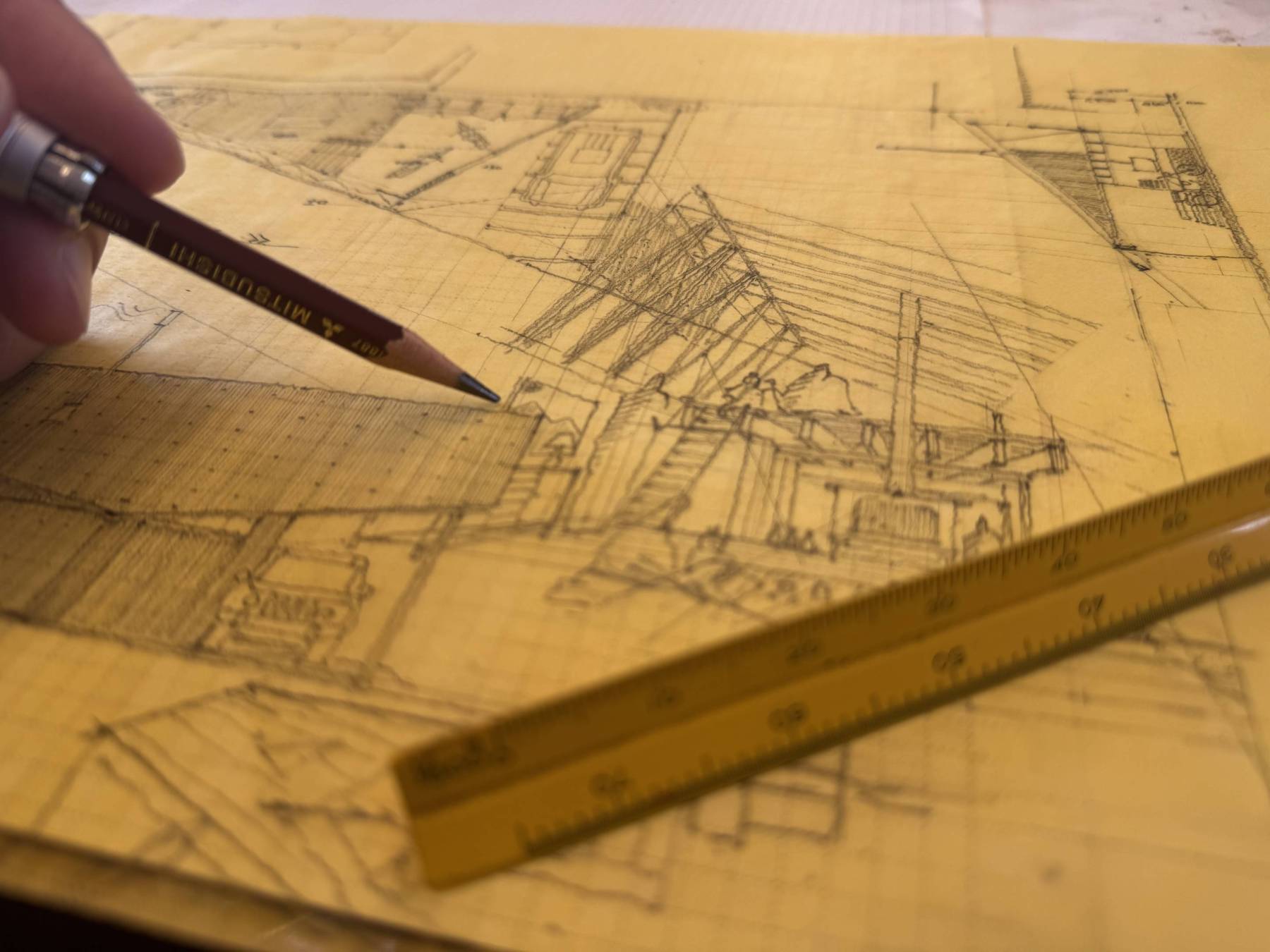
②工業製品に頼らず、職人や素材の工夫によってローコストを実現
・壁紙(内装工事)、タイル(タイル工事)、塗り壁(左官工事)など専門職人による仕上げを避け、大工だけで内外装を完結できる設計にすることで、施工コストを削減。
・通常メーカーでは使われない安価な素材も、意匠性を持たせた設計で活用することで、材料費を抑えながらも個性的な空間づくりが可能です。
出来るだけ固定観念を捨てきってコストを押さえながらクオリティーを上げていきたいと考えています。例えば下地材を仕上げ材にしたり、壁床天井全て同じ材料で仕上げてミニマムな空間を創ったりと想像力が必要不可欠になり楽しい設計の手法です。

③資金計画を含めたトータルサポートで無理のない家づくりを実現
・ファイナンシャルプランナーと連携し、土地費用・建物費用・諸経費を含めた総額での予算相談が可能です。
・建物費用のみに注目せず、土地とのバランスも含めた最適なプランを立てることで、全体として無駄のないコスト配分が可能になります。
④量販店の既製家具を活用してコストダウン
・建築家具はオーダーになるため高額になりがちですが、あらかじめ低コストな量販店の家具や収納ケースがぴったり収まるように設計することで、コストを抑えることができます。
⑤経費削減の工夫で、価格に還元
・ハウスメーカーのように住宅展示場を持たず、完成した住宅を引き渡し前にお借りして見学会を実施することで、展示場の維持費を削減。
・営業担当を置かず、設計者が直接接客を行うことで、人件費を抑え、適正な価格での提供を実現しています。
弊社7割のお客様が見学会にご来場いただいています。住宅展示場の様に見せる会場ではなくて実際に住まわれる家を見学いただくことは必ず参考になります。また、ご案内するスタッフは営業マンではなく設計担当者です。自分たちが力を入れたところや思い通りにいかなかったところ、うれしかったところなどリアルなお話を聞いてもらえたらと思います。その結果無駄な経費を使わなくお客様へ還元できると考えています。

ハイクオリティ住宅が実現できる理由
①オートクチュールな住宅設計
・外装や内装の仕上げにおいて、既製品にとらわれず、自由な発想で素材を選定しています。
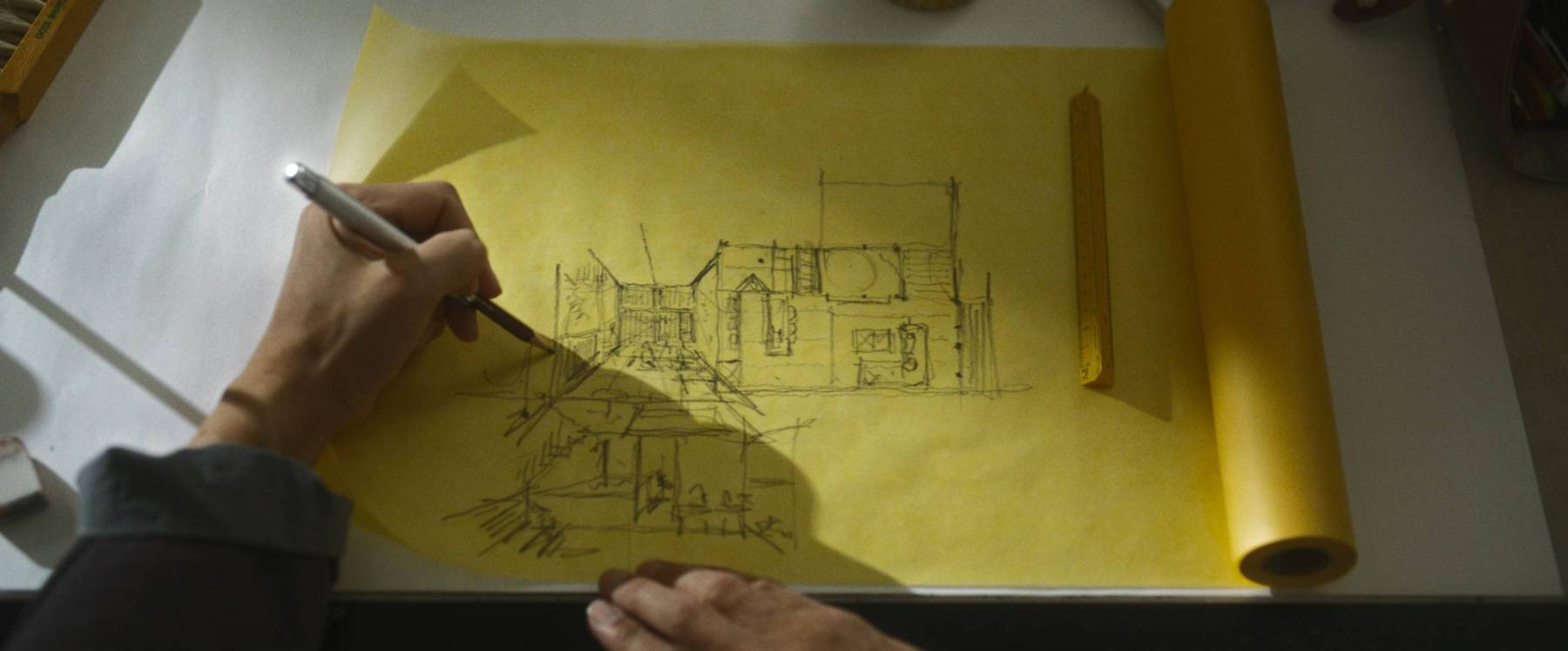
たとえば、屋根材には一般的な「屋根専用材」ではなく、あえて「波トタン」を使用することがあります。壁仕上げには、工場などで使われる「セメント木毛板」という下地材を仕上げとして採用したり、押し入れ用のベニヤ板を壁や天井に活用することもあります。また、床材についても、一般的なフローリングではなく、コンクリート基礎をそのまま仕上げとするケースもあります。
こうした工夫により、コストを抑えつつも素材の組み合わせでデザイン性を高め、独自の質感を持った空間を生み出しています。
・浴室に関しては、主流であるユニットバスを使用せず、「置きバス」を採用することで、コスト削減とメンテナンス性の向上を両立。また、トイレと浴室を一体のワンルーム空間とすることで、仕切り壁やドア1枚分のコストを省きながら、ホテルライクなデザインを実現できます。

・キッチンについても、システムキッチンにこだわらず、業務用の厨房設備を組み合わせることで、インダストリアルな雰囲気を演出し、デザイン性と実用性を兼ね備えた空間づくりが可能になります。

このように、固定観念を崩し一般的な常識や製品の枠を超えた設計提案によって、コストを抑えながらも高いクオリティを持つ住宅を実現しています。
②次世代へつなぐリノベーション対応型の家づくり
・「完成された家をつくる」のではなく、「住まいは変化していくもの」と捉え、将来を見据えた設計を行います。家族構成やライフスタイルの変化に合わせて、柔軟に対応できる設計を行うことが、結果として長く住み継がれる住まいにつながります。
・初期段階の家づくりですべてを完結させるのではなく、次世代へ引き継ぎ、時間とともにリノベーションを重ねていくことで、より質の高い住まいへと進化させていく——これが「風景のある家」の基本的なコンセプトです。

住まいを「一代限りの消費財」ではなく、「世代を超えて育てていく資産」として捉えることで、長く価値を持ち続ける家づくりを可能にします。

1970年栃木県生まれ。福山大学工学部建築学科卒。株式会社丹羽建築設計事務所、株式会社FORM設計(チーフディレクター)、株式会社3.3/Design(設計チーフ/専務取締役)を経て、2012年に風景のある家を設立。FMレディオモモ、RSKラジオなど多数出演。2004年から10年間福山大学工学部建築学科非常勤講師を経て2020年より岡山科学技術専門学校非常勤講師とし現在に至る。